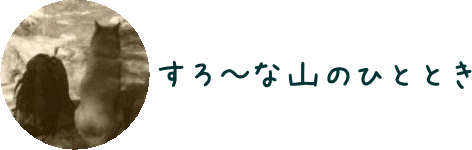タンナサワフタギ ハイノキ科ハイノキ属
溢れんばかりの緑の中にヤマボウシやエゴノキ、タンナサワフタギの白い花が清々しく咲く谷筋。
野鳥の囀り、水音が静かな谷に心地よく響く。
木々の花や岩場や草地に咲く花を楽しみながら緩々歩き^^
ハナイカダの果実 : ヤマウグイスカグラの果実
コツクバネウツギを覗きこむと…(o^―^o)ニコ ケハンショウヅルの蕾と影が絶妙
朽木や古木も一味添えて…ミヤマナルコユリ . トウゴクシソバタツナミ
しっとりと水滴を纏う花や果実
カマツカが咲き終わった5~6月に入れ替わるようにタンナサワフタギが谷筋などで咲き誇ります。
六甲山系、丹生山系の散策エリアではタンナサワフタギが多く見られ、類似種のサワフタギは生育してるのかは?
京北の山域でサワフタギをよく見かけましたが、白い小さな花はほぼ同じでした。
2種には幾つかの見分け方があるようです。
※ タンナサワフタギ:葉は幅3~5㎝の広倒卵形で葉の先端は長く尖る。果実は藍黒色。鋸歯はサワフタギより粗く尖る。
※ サワフタギ : 葉は2~4㎝の倒卵形~楕円形、葉の先端は短く尖る。果実は藍色
この谷筋のミヤマヨメナは別の谷筋の花より花茎の長さが短いようです(10㎝ほど)…。
ハンカイソウの花は蕾でしたが特徴ある葉は とても存在感あります。
フデリンドウが子房の中に種子を溜め、雨滴散布(雨水を溜め溢れ出る水と一緒に種子を流れ落す)の準備しています。
子房の両側に切れ込みが入っているのは、種子が流れ落ちやすい仕組みなんですね。
花の時期はは太陽光で開き夕刻や雨だと閉じる花が、種子の時期は雨天に開くんです。フデリンドウ凄いなあ!
雨後のフデリンドウは雨滴散布で種子が流れ落ちていました(違う個体)
紫斑の葉が魅力なトウゴクシソバタツナミが咲きはじめていた。
兵庫県のはシソバタツナミの変種といわれていますが、稀にシソバタツナミとトウゴクシソバタツナミの中間的なのもあるようです。
たまには じっくりと葉裏の腺点の有無や腺毛などルーペで観察しないとあかんな…と、思いつつも老眼の所為にしてスルー(^^ゞ
5月23.25.28日:丹生山系